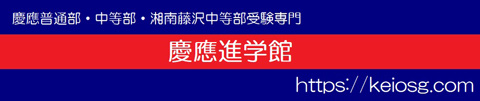本来カリキュラムテストというのは、そのカリキュラムを理解できているかを確認すればいいだけの話であって、相対評価を出す必要はありません。
カリキュラムテストはその意味では絶対評価であるべきなのです。100あるうち80わかっているのか、90わかっているのか。わかっていないところがあるとすればどこなのか、それを確認すればいい。
しかし、相対評価を加えると100わかっている子どもと、90わかっている子どもを区別する。絶対評価ではそれほど変わりがないと思える子を並べれば、当然順番がつくわけですが、今度はその偏差値が一人歩きする。
その集団は実はよくわかっている子どもの集団でみんな80くらいわかっているが、平均は偏差値50になります。
一方よくわかっていない子どもの集団でみんな50しかわかっていないが、平均は同じ偏差値50になる。
80くらいわかっている子と、50くらいわかっている子の評価が同じになってしまう。しかもそれをクラス分けや席順に使うから、偏差値ばかりに関心が行ってしまい、本当にどのくらいわかっているのか、という点には目が向かない。
50%しかわかっていなくても偏差値60が出たりすれば、安心してしまうことになりかねないのです。みんなができないから仕方がないのね、と考えてしまいがちですが、本当はその学習は不要だったかもしれないのです。
偏差値を考えるのはテストの範囲がなくなり、すべて実力勝負となってからで良いのです。それまでの間は、習ったことができるか、どのくらいわかっているか、に注目していないと、取りこぼしが多くなるから注意が必要です。
今日の田中貴.com
親子でがんばる中学受験
6年生の教室から
春期は算数をがんばろうか
中学受験 算数オンライン塾
2月27日の問題