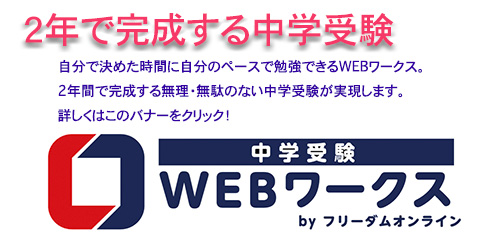粘って自分で答えを出そうとする子は、なかなか問題を解くのに時間がかかります。
だから、まあ、横で見ていてついヒントを出してしまいたくなる。
あるいは時間がないので、切り上げさせる場合もあるでしょう。答えを見て納得した気になっているかもしれない。
しかし、結局それでは力がついていない、ということは良くわかります。
自分で考えられるようになっている子が、最後は地力を見せて力をつけてくる。
「わかった」というのが格好だけのわかった、なのか。それとも本当にわかった、なのか。
自分で後からちゃんと解ける、というのは本当にわかった、でしょうが、そうでない子は「わかった気になっている」だけかもしれません。
で、そんなことにこだわっていたら、塾の問題なんか終らない、と思われるでしょうが、しかし、たくさんやってもボロボロになると、後で結局やり直さなければいけないことになる。
すべての問題を網羅する、なんて不可能なのですから、ある程度どんな問題でも対応できる、ようにするべきであり、そのためには子ども自身に「問題解決能力」を持たせないといけない。
それが結局自分で考えられるか、という視点になるのです。
Newフリーダム進学教室からのお知らせ
今日の田中貴.com
生殖に関する問題
6年生の教室から
短期間に集中すべき
慶應進学館から
出席日数
4年生の保護者のみなさまへ
中学受験パパママ塾「ONE」のご案内