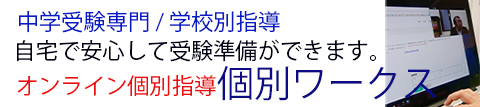月例テストとか、組み分けテストとか、まあ、いろいろ名称はあるものの、カリキュラムテストというのはその月の内容がどのくらいわかったのかを把握するためのものです。
しかし、組み分けということになると関心は順位とクラスに変わってしまう。ここが結構もったいない。
本来勉強は積み重ねですから、例えば電気について、発熱のしくみまではわかっているが、そのあとの計算問題ができないとか、直列の発熱はわかるけれど、並列の発熱はわからない、とか、まあ、いろいろ理解の度合いがあるわけで、当然、そのあとを積み重ねていかないといけない。
あるいはそういう問題が出ないような学校であれば、そこまでにしておいても良い、のです。
先日ある大手塾での公開模試は、記述系と非記述系に分けて問題構成がされており、記述系を志望とする場合のひとつの目安が提供されていましたが、すでに非記述系に志望校が決まっている場合は、本当のことを言えばあまり意味がないところもあるのです。
カリキュラムテストは、どこまでわかったか、を確認するのが第一義で、そこから次にどう発展させるかは、また後日やらなければいけないことなので、(というのも、次に新しいカリキュラムがやってくるからですが)そこは明確に把握して後の勉強に役立てないといけない。
しかし、偏差値やクラスに目が行くと、そのデータ把握ができていないことになるのです。せっかく塾としては正解率等を出しているので、ここはしっかり分析してください。
そしてそのデータを使って次の勉強を組み立てることが大事。この次はたぶん夏休みにやることが多いと思いますが、なるべく効率よく勉強を進めていくのにはむしろそのデータが大事です。
今日の田中貴.com
やる問題を減らして、じっくり解くことが大事
フリーダムオンライン-学習のヒント-
学習履歴データ化の目的
読んでいただいてありがとうございます。
![]()
にほんブログ村