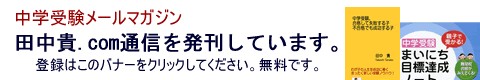子どもたちに論説文や説明文の解説をするとき、その文章をまず理解させる、ということが大事なので、いろいろなやり方を考えます。
ひとつの段落で、例えば例をあげてみる、他のことばで置き換えてみる、子どもたちにどういう意味か聞いてみる。
しかし、最近の入試問題はとにかく長いので、それをひとつひとつやっていくとあっという間に時間が経ってしまいます。
それでもあえて時間をかけてやっていかないと、子どもたちの解答はなかなか悲惨なことになりやすい。
今の入試問題に採録される問題のレベルは高校受験のそれとそう変わらない。だから、子どもたちはこれまでもたくさんの難しい文章を読んできてはいるのですが、果たして本当にわかっているのか?ということを考えてみると、上滑りになっている可能性が高いのです。
そこで、良くやる方法が要約を書いてもらうこと。
といって長い文章の要約を書かせる、などということになると子どもたちにとってもかなり絶望的なことになるので、いくつかの段落ごとに「何をいっているか」をなるべく短く書いてもらう。
そうすると、一番多いのは文のコピーです。
つまりその段落でここが一番大事だろうということをコピーしている。
「で、その意味は?」
「だから、・・・・」
といってまたコピーした文を読んでいるわけだけれど、実は本当はわかっていない。
しかし、そのひとつひとつをかみ砕いていくと、だんだん「そういうことなのか」という理解が進んでいく。
小学生にとって国語の文章の読解は実はそれほど時間がかかるものなのです。だから、そんなに一気に本当はできるわけがない。
しかし、できている。
なぜか?
結局わかっていないまま、進んでいるだけのことが多いからです。
国語はすべての教科の基礎ですが、そこが上滑りしているとなかなかできるようにならない。こういう作業は本当は4・5年生のうちにやっておきたいところではあるのですが・・・。
=============================================================
今日の田中貴.com
平面図形の問題
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應中等部学校説明会
==============================================================

==============================================================

「映像教材、これでわかる比と速さ」(田中貴)
==============================================================