過去問をやっていくと、その学校の出題パターンみたいなものはわかってきます。
例えば国語については長文が2題と、漢字。記述は3問。長い記述が50字前後、とか。
あるいは理科だと物理、化学、生物、地学から1問ずつ。とか。
で、それがだんだん高じてくると、
「昨年、電気が出たから、今年は出ない」
とか、
「しばらく音が出ていないから、そろそろ」
みたいなことを考えたくなってきます。
まあ、しぼった方が勉強はしやすいが、実は結構ヤマがあたったときが怖い。
つまり「これはチャンス!」と思ったが、意外にできなかったりして、あせったりする。あるいは突き進むあまり、問題を読み飛ばしたり。
また、そういう予想が外れたりすると
「今年は傾向が変わった」
みたいな話になりやすいのですが、しかし、良く良く問題を読んでみると、学校が求める人材像がそう変わっているわけではありません。
中学入試は独自入試ですから、学校の先生が問題を作る。しかし、それには充分な検討が重ねられています。我が校に迎えるべきは~のような人材、みたいな人材像があるので、それがわかるような問題を作る。
記述を出すのは、その後レポートで苦しまず、自分の考えが表明できる子を取りたいから。
長い文章や資料を読ませるのは、十分に研究しようという気概を持っていてほしいから。
というような考えで問題は作られているので、当然のことながらその人物像に沿った問題が出ています。
だから、あまりヤマをかけて、自分の視点を狭くしすぎてはいけません。
多少なりとも「どんな問題が出ても驚かない」胆力は必要で、そのためにもあまりヤマをかけすぎないようにしましょう。
==============================================================
今日の田中貴.com
第112回 ベストな状態で試合に臨む
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
12月4日の問題
==============================================================
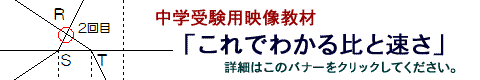
==============================================================
お知らせ
算数5年後期16回 算数オンライン塾「和と差に関する問題」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================
