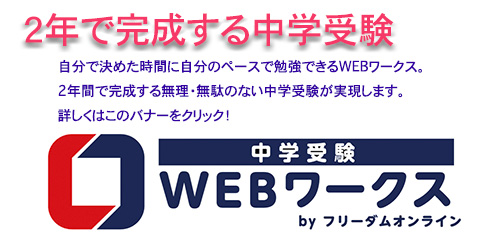最初は何とか自分の力で解くことにこだわっていた子も、模擬試験や合格可能性の判定が出てくると、段々考えが変わってきます。
時間内に解かないといけない。
とすると、この方法ではダメ。
じゃあ、どう解けばいいのか?
実際に数を当てはめてみたり、すべて書き出したりしているところもあるわけで、もっと簡単に解ける方法を考えるようになる。
あるいは調べたり、先生に聞いたり、ということもできるでしょう。
意識がそちらに行くかどうか、というのが次の段階。
ただし、自分で解き上げることに最初こだわっていないと、なかなか力がつかないことも事実。
自分で苦労する分、上手い解き方が良くわかるところはあるのです。
ということで、少しずつ子どもたちの意識が変わってくると、さらに力がついてくるでしょう。
Newフリーダム進学教室からのお知らせ
今日の田中貴.com
高校受験と中学受験の偏差値
6年生の教室から
パッチをあてる
慶應進学館から
慶應の理科
4年生の保護者のみなさまへ
中学受験パパママ塾「ONE」のご案内