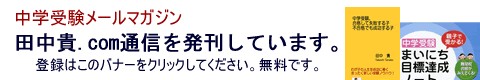電気の結構面倒な計算問題を教えていました。
もちろん、そんなに簡単にわかるような問題ではない。
何回か繰り返して説明をしているわけですが、それでもまだピンときてない。
でも、これは当たり前だと思うのです。難しいし、面倒だ。
で、これがみんなできなければいけないか、といえば多分、そんなことはない。
こういう問題が出る学校はやはり限られる。そんなのは過去問を見れば一目瞭然。10年分の過去問を見ていて出ていなければ、まず出ることはないのです。
でも、出るかもしれない。確かにそうでしょうが、しかし、そういう場合、なかなか出来る子は多くないから、出来なくても多分合否に大きな影響はないのです。
だから、カリキュラムでは扱うが、その後の指導では最早やらない、ということはたくさんある。
やはりやらなければいけないのは「良く出る問題」です。「出そうな問題」といってもいいでしょう。
出そうな問題ができないのなら、それをやるのが優先順位として正しいのです。
出そうにない問題は、まあ、気にしないことです。
今日の田中貴.com
第262回 すべての解法を覚える必要はない
6年生の教室から
わからなくなったところを見つける
今日の慶應義塾進学情報
中等部、算数の入試傾向