12月の最後の模擬試験ぐらいから、その子の調子は下降線を描き始めました。
勉強は、まじめにやっているように見えるが、とにかく間違える。ミスも多い。一番いけないのは、とにかく問題文を良く読まないこと。
急ぎの虫が絶好調なのか、とにかく半分読んで、もう問題を決めてしまっている。
特に社会はひどくて、本人は最初の1行を読んだだけで、江戸時代と決めているが、実は室町時代だったりして、もういけない。
その結果として、過去問やクラスのテスト演習はもうぼろぼろになる。
さすがに本人も青くなってきて、
「僕ってばか?」
みたいな感じになってきました。
で、まず本人に言い聞かせたのは、力はどこにもいかないこと。
つまり学力がついた以上、そう簡単にはなくならない。しかし、テストで間違えるというのは学力があってもやることだということ。
僕の力はどこかに行ってしまったのではないか?みたいな気持ちは捨てさせるようにしました。
次に原因の撲滅。なぜ、急ぐのか?
「え、だって間に合わないもん」
つまり、彼は間に合わない、という恐怖観念があるわけです。
「7割ができて満点でも70点。全部やって7割しか合ってなくても70点だけど、どっちが受かる?」
「え、その話は聞いた。全部手を付けなくても、手を付けた問題が全部できればいいんでしょ?」
「そういうこと。」
「わかってるんだけどねえ。やっぱり、ほら、全部やって全部できた方がいいじゃない?」
で、この点も何回か話をして本人はとにかくあせらない、ということに決めました。
そう、大事なのは決めること。
解っていても「あせらない」と決めないと、ついあせるものなのです。
で、具体的には少しやさしめの問題を解かせました。これはいつものパターン。できるんだ、ということを確認させることが大事。それでも最初はぽろぽろ間違えてました。
そのまま、冬期講習突入。
相変わらず、ちょこちょこミスはしていましたが、式と計算はその場で見直すようになり、また答えが出たら、もう一度問題は読む、というルーティンも守り始めました。
そんな中。
クラスのテストで満点をとった。
そんなに問題数が多くなかったのが幸いしたとは思うのです。つまりたくさんあると、ミス率が高い子はやはり満点はとれない。しかし、問題数が多くなかった分、うまくまとめられた。
「ここはチャンスだ!」
とほめまくりました。もう洗脳に近いかもしれない。
「いやあ、字もきれいになったし、式は確認するし。問題はもう一度読んでるし。こうやればいいんだよ。素晴らしいね!」
あとでお母さんに聞いた話では、その満点の答案はどうもお守りになったらしいです。
ここから、彼のV字回復が始まります。その後、満点はなかなかとれなかったが、それでも明らかにミスは減り、合格点レベルにはまとまってきて、無事第一志望に合格しました。
スランプは突然やってきます。
そして、本人の自信をなくさせます。
本当は、力はどこにもいっていない。ただ、やり方がまずかったり、ちょっと注意が足りないだけ。でも、それだけで間違えば点数は大幅に下がるものなのです。
こういうときはあわててはいけない。
どうしましょ?みたいな顔をしてしまうと、さらに本人の自信がなくなります。
まずはしっかり話をして、なぜ間違うのかの原因を探ることです。あとでやればできる、ということであるならば、明らかに最初の問題へのアプローチに問題があるわけだから、そこを修正する。
修正しても、またミスは出ることにはなるのだけれど、そこをまた修正する、という繰り返しの中で精度が上がって行けばいいのです。
そしてもうひとつ大事なことは、
「うまくいったときは大いにほめること」
まぐれでしょ、なんて言ってはいけない。ここは挽回のチャンスなのですから、大いにほめてあげてください。
==============================================================
今日の田中貴.com
名門校は受験指導をしない?
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
難しければ合格点は下がる
==============================================================
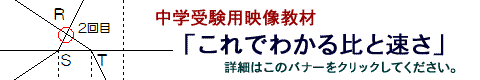
==============================================================
お知らせ
算数5年後期17回 算数オンライン塾「図形の移動(1)」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================
