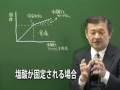塾の先生に「問題をよく読む」と注意を受けている子どもたちは多いでしょう。
確かに、「問題をよく読む」というのは大事なことなのですが、「そんなの、わかってる」と多くの子どもたちは思っているでしょう。
ただ、本当は「問題をよく読む」読み方を実践していないことが多い。
子どもがミスを起こす一番のタイミングは
「わかった!」
と思う時なのです。
例えば算数の問題を解いているとき、ある解き方を思いつく。これだ、きっと、こうだ。
そうなると夢中になって解いていくでしょう。そして答えが出た!
この瞬間に間違える。この段階で本人が今、答えと思っているものが実は求められているものではない。
ここがポイントなのです。
だから答えが出たと思ったときに、
「ここで問題文をもう一度読む」
が正しい読み方なのです。
できる子どもたちも間違えます。しかし、彼らはここで修正できる力を持っている。この瞬間にもう一度問題を読み直すというか、確認すると
「おっと、お父さんの時速か。」
ということに気が付くのです。
注意は具体的でなければいけません。つまり何をすれば、「問題をよく読む」ことになるのか指示していないと、注意は精神論になってしまう。
「気持ちが足りないから、ミスするんだ」
いいえ、違います。具体的にミスをしない工夫ができていない。
良く私は「心配はするな、工夫だけしなさい。」と子どもたちに言います。
どういう工夫をするか、具体的な工夫を指示します。
これを過去問でも、普段のプリントでも、しっかりやれるようになると、ミスは激減します。
今は過去問や問題をやるのに、出来を議論するよりは、むしろこういう過程をチェックすることが大事です。
例えば、よく塾の先生に
「問題文の大事なところには下線を引きなさい」
と言われている子もいるでしょう。しかし、それも「答えが出たときに見直す」ということができていないと、効果は少ないのです。
ぜひ、実践練習をしてください。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================