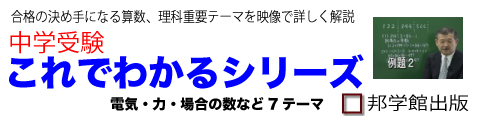わからない問題は、まあ、解答、解説を読む、というのがオーソドックスな学習法なのですが、しかし、どのくらい問題を考えたか、でその吸収力は違います。
結構考えて、あーでもない、こーでもない、といじくった後だと、ちょっと見ただけで「あ、そうか」と自分で解き始めたりする。
一方、あまり考えていないと、解説を読んでもよく分からない。特に上位校の問題はそうです。
解説文が言っている意味がわからない。なぜこうなるの?
こういう時に先生に教えてもらっても、五分五分という感じでしょうか。土台よく考えていないので、ピンとくることがないのです。
だいたい15分ぐらいは考えてもらいたいと思っています。しかし、そんなに考えていると、全然進まない。これも事実。
ただ、いい加減に進むぐらいなら、1問でもものにした方が良いのです。土台、毎年広がっている出題範囲を全部カバーするなど相当厳しい。したがって子どもの対応力を上げるしかないのです。
だから、じっくり考えさせないといけない。最近の学習法を見ていると、まったく逆の方向に進んでいる。
やはり粘れる子はできるようになるので、がんばって15分は考えてみましょう。
New!!フリーダムオンラインからのお知らせ
今日の田中貴.com
比重のかけ方
算数オンライン塾
5月16日の問題